医薬ビジランス研究所では、抗うつ剤のパロキセチンの毒性を検討してきましたが、今回は胎児や新生児に離脱症候群対する毒性を検討し、報告書にまとめたので公開いたします。
ラット新生児の4日までの死亡率が、ヒト常用量のレベルで20%から76%に達していました(図A)。
ヒトでも、外国の報告では、妊娠後期に使用した場合に22%の新生児が呼吸困難やけいれんなどの新生児離脱症候群を起こしていたと報告されています(図B)。
日本においても、国への先天異常や新生児離脱症候群の報告がSSRI関連で合計100件ありました。そのうちの87件と、大半の例でパキシルが使用されていました。
パキシルでは、新生児離脱症候群関連症状が68件、先天異常が19件報告されていました。フルボキサミン(ルボックス、デプロメール)など、他のSSRIなどでは新生児呼吸窮迫症候群が13件ありましたが、先天異常は報告されていませんでした。
当研究所で解析した結果、推定使用人数あたりの報告数を比較すると、パキシルはフルボキサミンに比較して新生児離脱症候群関連症状を8倍起こしやすく、先天異常は50倍以上起こしやすいと推定されました。
パキシルは、犯罪にもつながる攻撃性や他害行為も、他の抗うつ剤に比較して数倍起こしやすいと当研究所の解析結果から推定されたのですが、胎児・新生児に対しても極めて危険であり、妊娠女性、妊娠可能な女性には使用してはならないと考えます。
以下は、最も重要なグラフ(図AとB)と、まとめです。詳細は報告書を参照ください。
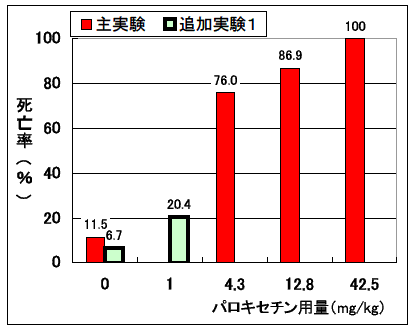
1mg/kg群は、追加実験1のデータ。
1mg/kgは体重50kgの人で10mg/日に相当し、4.3mg/kgは43mg/日に相当。
全ての群で、対照群に対して有意であった(p<0.0001)。
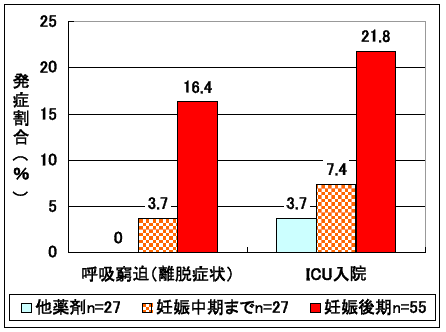
文献14)のデータより筆者作図。
呼吸窮迫(離脱症状)の、対照群(他薬剤+妊娠中期まで服用)に対する
粗オッズ比10.35(1.27-84.67)、調整オッズ比 9.53(1.14-79.3)。
パロキセチンの催奇形作用以外の生殖毒性、とくに、承認申請概要に記載された動物の新生児毒性の結果を分析し、ヒト新生児の離脱症候群および持続性肺高血圧症との関連について論じた。
動物実験で最も顕著であった毒性は、新生児の死亡率の増加であった。ヒトでの常用量上限(1日40mg)に相当する4.3mg/kgでは、新生児の4分の3が4日までに死亡し(対照群11.5%)、ヒトで常用量下限(10mg)に相当する1 mg/kgでも5分の1(対照群6.7%)が4日までに死亡した。4日死亡は対照群に比してオッズ比3.51(95%信頼区間2.18-5.65、p<0.0001)であった。対照群の死亡が多い追加実験2つ(7日死亡)を併合した場合でも、オッズ比は2.42(95%信頼区間1.79,3.26、P < 0.0001)であり、ヒト常用量相当レベルでラットの新生児死亡が増加することは疑いないといえる。
親動物(雄メスとも)に用量依存性の有意な死亡、不交配、不交尾、不妊(不受胎)、流産(全吸収)、着床後胎児の死亡、胎児の低体重、新生児の死亡(4日または7日以内)を認めた。雄のみが使用した場合でも不妊が増加した。雄では、精子数の減少や精子の運動性の低下、精巣上体の腫大や膿瘍、精液瘤、精細管萎縮なども認められた。器官形成期に使用した場合に骨格の変異が用量依存性に有意に増加した。
SSRIを使用した母親から生まれたヒト新生児離脱症候群の最初の症例報告は1993年であり、この例ではフルオキセチンが使用されていた、パロキセチンが関係した新生児離脱症候群は1997年に第1例が報告された。対照群を設けたコホート研究で、妊娠後期にパロキセチンを使用した場合22%の新生児に、けいれんを主とした離脱症候群が出現した(対照群5.6%)。パロキセチンを妊娠後期に使用した場合、呼吸窮迫のオッズ比は10.35(1.27-84.67)、調整オッズ比は9.53(1.14-79.3)であった。
また、症例対照研究の結果で、持続性の肺動脈高血圧の危険度が、SSRIを用いない場合に比してSSRI全体で6.1倍(調整オッズ比)、パロキセチンで25倍(オッズ比)となりうることが示された。
日本における使用患者数に対する自発報告例数の頻度のフルボキサミンに対するパロキセチンのオッズ比は、新生児離脱症候群関連でオッズ比が8.41(p<0.0001)、先天性心疾患を中心とする先天異常で54.6(p<0.0001)であった。この点からもSSRIの危険度が高いといえる。
妊娠後期のSSRIへの曝露は出生後の新生児に、易刺激性やけいれんを中心とする離脱症状を高頻度に引き起こすことは確実である。パロキセチン離脱の影響は、持続性の肺高血圧の危険を招き、ひいては心房中隔欠損や心室中隔欠損の自然閉鎖が阻害され永続的になる危険性がある。また、精神神経の行動発達に悪影響を及ぼす可能性が動物実験の結果からも具体的に懸念される。
パロキセチンは、妊娠中はもちろん、妊娠可能な女性には禁忌とすべきである。ただし、現在使用している場合には、減量のうえ中止すべきと考える。添付文書には、警告欄に、先天異常の危険が高まること、重篤な離脱症状が22〜32%にもなること、持続性肺高血圧の危険が25倍にも高まることなどについて記載すべきである。