4月19日深夜3時、読売新聞のインターネット版は、
厚労省研究班がタミフル、異常行動「否定できず」 10代再開に影響
との見出しで、次のように報じた。
「これでようやく厚労省は因果関係を認めることになるのか」と思われた方も多いかもしれない。しかし、そう考えてよいのでしょうか。たぶん、問題は解決しないでしょう。
なぜなら、
06/07の大規模疫学調査の第一次予備解析結果が2007.12.25に公表され、それに対して、当センターはその解析方法の誤りを指摘し(速報No101全体:2008.01.14)、廣田班へ、公開質問状も提出した(速報No102:2008.02.09)。
厚労省臨床作業班(WG)は、2008.7.10第7回会合で、その中間報告の結果を踏まえ、基本的間違いを踏襲したまま、タミフルと突然死を含む精神神経症状との因果関係を示す所見は検出されなかった、と表明した。
中間報告に対しても直ちに批判し(速報No108:2008.07.11)、海外にも発信した(速報No114:2008.08.09)。
この問題は、日本臨床薬理学会でも重視され、年次総会においてシンポジウムが08.12.04開催された。このシンポジウムでも、明確に中間報告の解析方法の誤りが指摘された(速報No116:2008.12.08)。
ところが、今回の最終報告でも、これまでに指摘された科学的誤り、すなわち、本来タミフル群の異常行動発症者の一部を抜き出し、非タミフル群に追加するという、とんでもない計算間違いを踏襲したままである。
重症例に限ると1.54倍であるとして、因果関係は否定できないとされたが、有意の差ではなく、本来高度に有意差のあるデータが完全に薄められてしまっている。これでは、因果関係を認めることとはほど遠いデータであり、かえって問題の本質を見失わせることになり危険である。4月24日に厚生労働省から報告書を入手することができたので、その問題点を検討する。
厚生労働省の研究班「インフルエンザ随伴症状の発現状況に関する調査研究」(分担研究者:廣田良夫大阪市立大学大学院医学研究科公衆衛生学教室教授)
調査方法の基本、解析方法の基本、間違いの基本は、中間報告とほぼ同じである。違いは、受診前異常行動発症者と、受診後タミフル服用前の異常行動発症者数が若干異なるのみである。
廣田班調査中間解析でも最終報告でも、受診前に異常行動を起こした子を除外した。この除外は、タミフル処方群にも、他剤処方群にも適用されているため、大きなバイアスは生じない。また、受診前に異常行動を起こした子の割合は(最終報告で)
タミフル処方群 :3.43%(268/7813)
他薬剤処方群:3.77%(83/2204) オッズ比0.91(0.70-1.18)p=0.449
もともと異常行動を起した子は、両群に同じ程度含まれているが、どちらかといえば、タミフル処方群の方にやや少ない目である。したがって、タミフル処方群に異常行動の頻度が高く出るようには働かない。したがって、集計上の不都合は特段生じない。
タミフル処方群からは、タミフル服用前に異常行動を起こした子を除外
他薬剤処方群からは、他薬剤を服用前に異常行動を起こした子は除外されず
しかも、タミフル処方群の早期異常行動発現例を追加
これでは、薬剤以外でもともと異常行動を起しやすい子が、
タミフル処方群からは除かれ、著しく少なくなり、
他薬剤処方群には加えられ、著しく多くなる。
「タミフルは異常行動を起こさない」(タミフルは異常行動とは無関係)と仮定すると、廣田班方法では常にタミフル群が非タミフル群より、異常行動を起しにくくなる。
まず、対象人数(n)、および、背景因子が同一で、処方に「タミフル」を含むか否かだけが異なる2群を想定する。そして、
異常行動割合は (a+b)/n(中間報告、最終報告)である。
タミフル処方群も他薬剤処方群も、いずれもオッズ比は1となり仮定と一致する(図1)。
| 異常行動起した人数 | 異常行動のない人数 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 「タミフル服用群」 | b | c | (n-a) |
| 「タミフル非服用群」 | 2a+b | c | (n+a) |
となる。
したがって、タミフル処方群の異常行動に関するオッズ比はb/(2a+b)(中間報告、最終報告)である。このオッズ比は、aが0でない限りORは常に1より小さくなり、仮定と矛盾した結果が得られるため、計算過程のいずれかに間違いがあるといえる。
ITT法との違いは、aをタミフル処方群から他薬剤処方群に移動しただけである。したがって、この処理が間違いの原因であると結論付けられる。
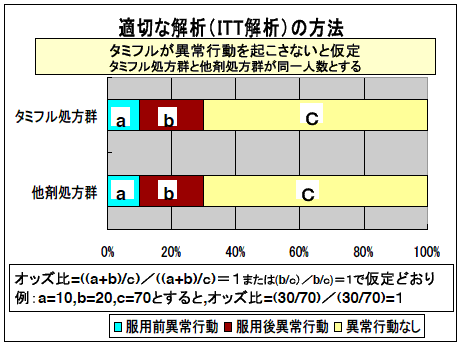
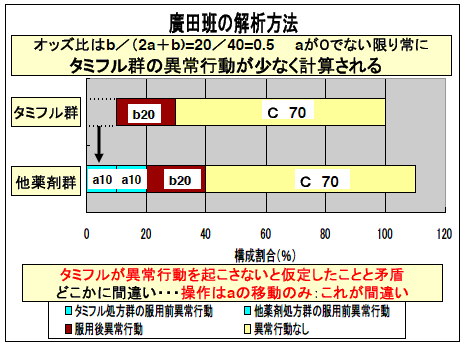
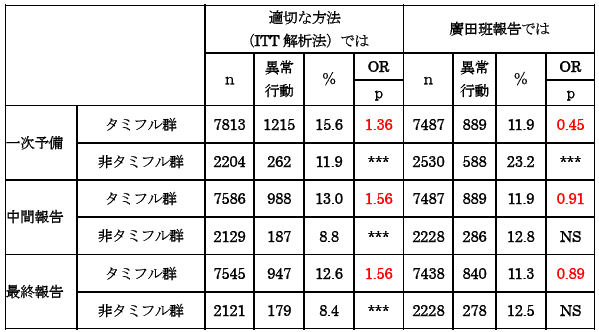
「なお、介入群研究におけるいわゆるintention-to-treat analysisの手法に基づき、これらの対象者を「オセルタミビル服用あり」として取り扱うべき、との議論があるが、本調査が、前向き観察研究デザインであることを踏まえると、outcome事象発生後に受けた曝露を、「outcome事象発症前にうけた」として取り扱うことと同義となる。したがって、そのようなデータの取り扱いは不適切であると判断した。」
注:intention-to-treat analysisは、ITT解析を意味する。
廣田班の最終報告では「outcome事象発生後に受けた曝露を、「outcome事象発症前にうけた」として取り扱うことと同義」としている。しかし、この考えでは、自己矛盾が生じる。
異常行動を起こしうる曝露因子を、タミフルに限れば、異常行動発症後のタミフル服用を、「outcome事象発症前の暴露」とすることになる。
しかし、異常行動を起こしうる曝露因子はタミフルだけではない。非タミフル群には、アマンタジンが0.8%に、ザナミビルは38%に、アセトアミノフェンは50%に、非ステロイド抗炎症剤も4.7%に、抗菌剤が20.8%に、その他が65.9%に処方されている。「その他」の中には、おそらく抗ヒスタミン剤や気管支拡張剤などが含まれていると思われる。こうした薬剤が全く異常行動発現に無関係とは決していえない。なお、タミフル服用群には、アマンタジンが0.04%に、ザナミビルは0.3%に、アセトアミノフェンは53.2%に、非ステロイド抗炎症剤が3.6%に、抗菌剤が17.0%に、その他が53.1%に処方されていた。
そして、タミフル非処方群(他薬剤処方群)には、これらの薬剤を服用前に異常行動を起こした子が多数いるはずである。これら薬剤を服用前に異常行動を起こした子をこの群に入れておくことは、「outcome事象発生後に受けた曝露を、「outcome事象発症前にうけた」として取り扱うことと同義」である。
したがって、廣田班は、「outcome事象発生後に受けた曝露を、「outcome事象発症前にうけた」として取り扱うことと同義」とすることは、自らの分類の間違いを指摘するという矛盾を犯しているといえる。
当センターでは、タミフル服用前の異常行動早期発症例を「オセルタミビル服用あり」として取り扱うべきとは言っていない。
タミフル処方群にも、タミフル非処方群(他薬剤処方群)にも、「受診後薬剤服用前の早期異常行動発症例(早期事象発現例)」が生じるため、廣田班報告で指摘する「outcome事象発生後に受けた曝露を、「outcome事象発症前にうけた」として取り扱う」ことを避けるために、タミフル処方群から早期事象発現例を除くのであれば、タミフル非処方群(他薬剤処方群)からも公平に除くべきであると主張しているのである。
廣田班では、そうした集計をしようとすればできるデータを持っている。当センターは、2008年1月から、廣田班に対して、そうした集計をすべきことを提言しているが、廣田班はしていない。
廣田班では、上記のような最も適切な集計をしていないから、公表されたデータで可能な限り公平な比較のための集計をしようとすれば、ITT解析をせざるをえないと主張しているのである。
そして、この方法には、タミフル処方群にも、タミフル非処方群(他薬剤処方群)にも、非特異的な異常行動は同様に発症するので、タミフルが異常行動と関係する場合には、その危険度を減少させる方向に作用するが、危険度を増大する方向には決して働かないという利点がある。
<スライド>も作成しましたので、それもご参照ください。最終報告では、中間報告のような、数字の移動の状況が、報告書を見るだけでは分かり難いので、スライドには、廣田班の中間報告に習って、最終報告の数字の移動の状況を示しておきました。